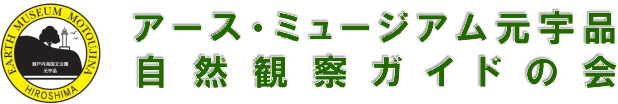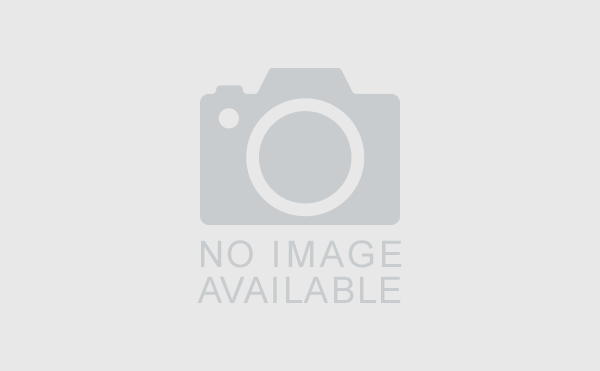冬を待つ元宇品のヨコヅナサシガメ
*このコラムには虫の拡大写真や摂餌映像がありますので苦手な方はご注意ください。
深まる秋にハゼノキが色づき始めた元宇品です。9月10月はスズメバチが途切れることなく姿を見せていましたが、涼しくなって蜂の脅威も無くなり展望台周辺を見ていると…
「うーん、これは幼体だな…ヨコヅナサシガメの!」

2025.10.26
サシガメは肉食性のカメムシで、注射針のような口で獲物を突き刺して体液を吸います。
腹側にフリルのように広がった白黒模様が横綱の化粧まわしに似ていることから、ヨコヅナサシガメと呼ばれました。
目を凝らすとここにもあそこにもという感じで、大木の木の皮の深いしわや剥がれの裏に2匹、3匹と見えます。体の一部が赤いので少し前に脱皮したようです。ゆっくりと動くのでたくさん写真を撮って帰りました。
帰宅後撮影した写真を見ると、樹皮の上のサシガメは輪郭がぼやけて冴えない写真ばかりです。
「私、写真、下手すぎる!」

↑は獲物、この写真に4匹のサシガメがいます
しかしよく見てみると、獲物となったゴミムシのような昆虫の翅(赤い↑)は鮮明に映っています。
「サシガメは糠をまぶしたみたいだ…。」「本当にヨコヅナサシガメ?」
インターネットで情報を取りつつ、手許の図鑑を見ながら悩んでしまいました。
・ヨコヅナサシガメの体の表面に何か理由があるとか?
・樹皮に擬態して敵から見えづらくしているとか?
「もう一度現地に行くしかない!」

調べてみると、折れたツブラジイの大木の隣の木にもヨコヅナサシガメの幼体を見つけました。どれもだいたい同じ大きさです。2匹連れて帰って観察することにしました。
拡大して見てみると…

腹側周辺を拡大、左下の凸部は反射で光っている
「毛というよりも髭だな…白い部位にも黒い髭が生えるのか!」
生えている毛は…髭剃り後に伸びた無精髭のような「太い毛」が粗く生えています。ピアノの鍵盤を思わせる白黒の腹側部は緩く波打っています(大人になるとフリルのように波打ちます)し、凹凸した体の表面はたっぷりと漆を塗ったようです。
「この体なら木の洞から外に出ていても、乱反射などで目に付きにくいのかも知れない…。」
連れて帰ってからサシガメが何も食べていないので、ペットショップでミルワーム(生餌のイモムシ)を買ってきました。
1匹が直ぐに反応してゆっくりとイモムシに近づきます。
サシガメは注射針のような鋭い口吻(こうふん)でイモムシの胸のあたりを刺しました。イモムシも反撃しますが、サシガメはひっくり返されても口吻を刺したまま耐えます。サシガメはイモムシを大人しくさせる毒と消化液を注入し体外消化したものを口吻で吸い上げます。吸汁は20分に及びました。
「えぇ~、このお腹はパンパン過ぎる~」
2匹のサシガメですが、イモムシを吸汁した1匹としなかった1匹のお腹を比べてください!

同じ大きさの2匹

吸汁したサシガメの腹部(右)
凹んでいた背中がぽこんと凸っていますし、お腹は幅も厚みも明らかに大きく厚く膨らんで、驚きとともに夜は更けていきました。
翌週もツブラジイの大木を訪問しました。サシガメがいる木の周辺に餌になった虫の死骸が転がっているという情報があったのです。さらに隣の大木を回り込むと…
「わわっ、黒い蜂球……じゃない!サシガメ球だーー!」
中心には獲物がいると思われますが、口吻を刺そうとしてサシガメ達が重なり球状になっています。それに気づいた別のサシガメもやってきました。

2025.11.8
数えてみると周辺合わせて15匹以上、こんな多くのサシガメに口吻を突き立てられる虫もたまったものではないでしょう。このように子どものヨコヅナサシガメは集団で獲物を捕らえて分け合うということです。吸汁が終わったサシガメは随時離れていきました。

最後に残った一団
吸汁は1時間ほど続き、やがてサシガメの数も減り体液を吸われた虫の姿が現れました。胸のあたりが大きく壊れており、口吻の威力が伺えます。よく見ると大木の周りには被害にあったと思われる昆虫の死骸がいつくかありました。

サシガメと木の周りの死骸:真ん中が今回の犠牲者(虫)
ヨコヅナサシガメは主にサクラやエノキで発生する外来種です。6、7月ごろに樹洞などに産卵し20~30日で孵化。不完全変態なのでイモムシやサナギの期間はありません。孵化した幼虫は翅のない小さなヨコヅナサシガメの形をしています。幼虫はその後捕食活動に励み12月までに5令幼虫に成長し集団越冬します。成虫は5月頃に出現します。
調べているとやっと次のような記述にたどり着きました。
ヨコヅナサシガメは、多くの昆虫やクモ類を捕食するが、行動は緩慢である。鈍い動きで餌を捕ることができるのは、体色が生息している木の幹と同じ色でカモフラージュの役目を果たし、餌である昆虫やクモがこのカメムシに気付かず近寄ることによると推定される。
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所/自然探訪2008年4月 コクワガタの幼虫、ヨコヅナサシガメの幼虫
「体色はカモフラージュの意味がある!」
ぼやけた写真の考察は、まんざら的外れでもなかったようです。

苔むした樹皮の隙間に潜むヨコヅナサシガメの幼虫
成虫の期間は1か月ですが、幼虫期間は10か月に及びます。この長い幼虫時代…餌を捕り、脱皮を繰り返し、何とか無事に過ごして大人になり子孫を残さなければなりません。カモフラージュや集団摂餌に集団越冬…ヨコヅナサシガメにとって幼虫時代に生存のための工夫をすることは、種の存続のために大変有効なのかもしれません。
【参考】
樽 創, 2002. 小田原市城山競技場におけるヨコヅナサシガメの越冬状況 神奈川自然誌資料 2002 巻 23 号 p. 47-51
中尾舜一, 1954. ヨコヅナサシガメに関する生態学的研究.その分布および一般習性について.九州大学農学部学芸雑誌, 14 (3) : 319-328.
昆虫探検図鑑1600 川邊 透 全国農産教育協会 2014.7.31
虫のぬけがら図鑑 安田 守 ベレ出版 2021.7.25
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所/自然探訪2008年4月 コクワガタの幼虫、ヨコヅナサシガメの幼虫
アース・ミュージアム元宇品 自然観察ガイドの会
副代表 畑 久美