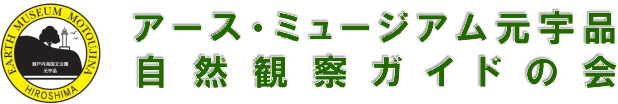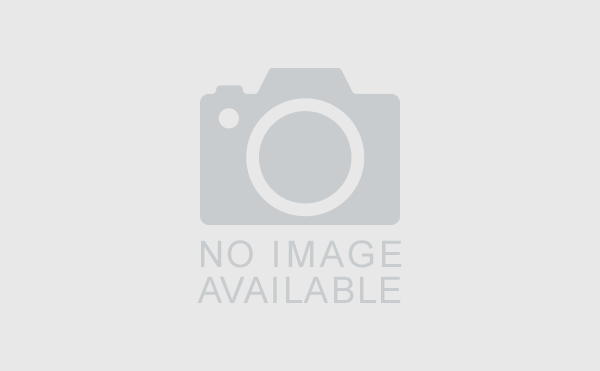元宇品のグンバイムシ
森の観察に行こうと宇品山のふもとにやってきました。春風に草の葉がそよいで、時々フジの花びらが降ってくる様についつい見入ってしまいました。

ここは宇品島の東側、森と人家の境目にある小さな社のならびに草むらが続いています。
「何かいるかしら…」
草むらに顔を近づけると小さな白い点が目に入りました。いやいや点というよりポップコーンの欠片のような…。

「おぉ、この形はグンバイムシでは⁈」
グンバイムシはカメムシの仲間で、形が相撲の軍配に似ているのでその名が付きました。
グンバイムシを英語では『Lace bug・レースバグ』と言います。翅や体にステンドグラスのような半透明の小窓を持ち、レース細工のような美しさです。わずか数ミリの虫ですが複雑で美しい造形に驚かされます。
研究者曰く、「この美しさは意味不明だ!」「もう少し大きかったら美麗昆虫として人気者になるに違いない」…。
「嬉しい!どんな可愛いレース編みの翅なのかしら…」
虫の付いた葉を一枚、持って帰ることにしました。
うわぁ、これこれ、エリザベス1世の肖像画に描かれそうなレース模様です。私がレース作家だったら、これを編んでみたい!

頭部には「とさか」のような帽状突起(中は空洞)、その両側は象の耳のように板状に張り出した翼突起、背面や周囲には細い棘が並んでいます。ぼんやりと茶色い斑紋が見られますが、前翅の後方に3つ並んだ丸い小窓が特徴的です。
どうやら北米原産の外来種『アワダチソウグンバイ』と思われます。
「うーむ、セイタカアワダチソウか…あの辺りにあったっけ…」

写真を見直すと確かにセイタカアワダチソウの若葉です。葉は汁を吸われて白く汚れて見えます。
アワダチソウグンバイは…1999年に兵庫県西宮市のセイタカアワダチソウで初確認され,急速に広がったよう…。本種は主に、林縁部のセイタカアワダチソウのロゼッタで成虫越冬し、4月中旬に第1世代幼虫が発生…。冬の低温には弱いようです。
農業被害もあるようですが、アワダチソウグンバイのフェロモンを調べることで、未開拓の新たな酵素遺伝子資源となりえるかもしれない、という報告もありました。
動きを観察すると歩きながら体を小刻みに揺らしています。ナナフシやカマキリも体を揺らすことが知られていますが、その理由は、風に揺れる様をまねたり、獲物との距離を測ったり…と様々に言われます。このグンバイムシの場合はどうなのでしょうか…擬態?威嚇?それとも?
調べてみると、アワダチソウグンバイの配偶行動にはマウントしたり,体を振動させたりする行動があるようですが、これがそうなのかは分かりませんでした。

2日後に現地を訪ねてみました。セイタカアワダチソウは草むらにまばらに生えていたのではなくて、ミカンの木の下にひと固まりの群落がありました。一昨日よりも少し背が高くなり、虫の数も減っているような…。成虫になったアワダチソウグンバイ達は飛び立っていったのでしょうか、春の時間は大急ぎで過ぎて行くようです。
【参考】
星野 滋(2011):植物防疫 第65巻 第11号広島県におけるアワダチソウグンバイの地理的分布 65_11_15.pdf
アワダチソウグンバイ-レースをまとった貴婦人?- – 全国農村教育協会 出版サイト
清水伸泰(2019): 環動昆 第30巻 第4号:161-168 untitled
アース・ミュージアム元宇品 自然観察ガイドの会
副代表 畑 久美