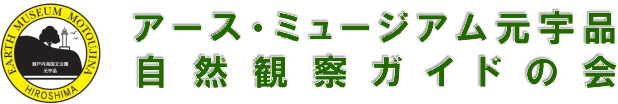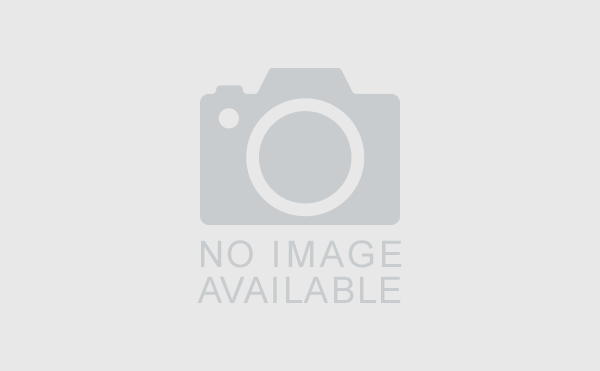海辺の生き物【アマクサアメフラシ】
6月には磯で海の生き物を観察する機会が多くなります。従来は灯台下の浜を小学校の観察フィールドとしていましたが,昨年から新たに広島港のに近い海岸を選定しています。
この日の干潮は15時42分、大潮で潮位25㎝です。前日見た「ババガセ」をもう一度観察したかったのです。

ババガセ 2023.6.16 元宇品
ここの磯は普段は平凡な岩のある砂浜という感じなのですが、大潮の干潮を狙って訪れると、低潮線付近で見られる生き物がすぐ近くの足元で見られるのです。

磯の観察を終えて、打ち上げ海藻の観察を始めました。今シーズンはミルに付くウミウシを探しています。潮が引き切った浜にはたくさんの海藻が打ち上げられており、一つ一つを丹念に見ていました。ふと目をやると海藻にもぐれた大きなホヤのようなものが目に入りました。
手を差し込んで引き上げようとしたら、ずるりとその重いこと!25㎝くらいあるようでした。
「うーっ、えーっ、もしかして!!」
海藻を除いて、裏返すと貝殻のかけらや砂粒がくっ付いてパン粉をまぶしたと言えばそれは大げさかな…とにかく、そうっと除いていくと…。

「うわぁ、やっぱりアメフラシだぁ!久しぶりの対面、元宇品で何年振りかしら~~」
軟体動物であるアメフラシはナメクジを大きくしたような体をしていて、背中には退化した薄い貝殻を隠しています。アメフラシは産卵のために浅瀬に来たところを波に打ち寄せられたのでしょう。
大喜びでアメフラシを潮だまりに運んで観察を始めます。あれっ、こんなに体を持ち上げて掴んでいるのにあの有名な「紫色の汁」を出しません。ふーむ、波間で揉まれているうちに汁は出し切ったのかな…??
じっと見ていると、何だか顔つきや体つきが普通のアメフラシと違っているような気がします。体に斑紋も見えませんが、模様は当てにできないか…。
「…アマクサアメフラシ?」
その後アメフラシとアマクサアメフラシの違いを調べてみました。
体色は変化に富み,色だけでは他のアメフラシ類と区別出来ない…
- 刺激したときに出す汁が白色(強い刺激でないと出さないのでそっとしてあげてほしいです)
- 足が吸盤状になっている
- 背中のひだが体後部でつながっている
刺激しても紫汁は出しませんでした。足が吸盤状になっていたか覚えていないのですが、貝殻のかけらや砂はたくさんくっ付いていました。アメフラシを掴んで粘液の付いた手を匂いましたが、「あれ?あんまり生臭くないなぁ~」と感じました。そうだ、背中のひだは・・・

後方でつながっているようです。
このアメフラシは「アマクサアメフラシ」と思われます。あぁ、もう一回目の前で確認したい!次の大潮で会えないかぁ~
打ち上げられた海藻と一緒に「海そうめん」とも言われるアメフラシの卵塊がありました。

よく見ると、細長いチューブの中に卵が見えます。

卵は卵嚢の中で孵化して変態し(トロコフォア幼生→ベリジャー幼生)海中を泳ぐ頃は小さな巻貝の貝殻を持っています。やがて海底を這いまわるようになり、貝殻も退化して受精後約50日で1.5~2㎝位の小さなアメフラシになります。
参考
生きもの好きの語る自然誌 鈴木雅大
アマクサアメフラシ Aplysia juliana (tonysharks.com)
写真で分かる磯の生き物図鑑 トンボ出版
アメフラシの採取・飼育と発生 矢島正博
アース・ミュージアム元宇品 自然観察ガイドの会
副代表 畑 久美